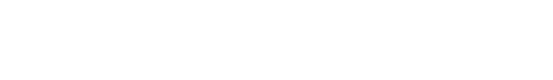今日は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの凄さと
フーガについて探究してみたい。
バッハの凄さ①平均律の普及に貢献
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
(1685年 - 1750年)は、
バロック時代と言われる
絶対王政時代の時代に生まれた。
そして、バッハが生まれた家族は
代々の音楽家の家系であり、非常に多くの
音楽家を輩出し、オルガンも
一族から学んでいた。
バッハが考えていたのは、
キリスト教的神学観から来る世界観であり、
音楽というものは
神を讃えるためのものであると
固く信じて育った。
バロックという時代は、絶対王政として
王族・貴族の宮殿にて音楽を奏でるための曲を
作曲していた時代であったが、
同時にキリスト教の宗教音楽として、
プロテスタントの信仰を持ち、
魂を信じ、人の心を音楽で癒し、
神の創らせた世界を調和し、
美しきものとするために、
人間に神が音楽を与えたのだと
考えていたのである。
ルネサンス時代までは、純正律という音階で
教会音階が使われていたが、
この時代、はじめて
「平均律」と言われるものが登場した。
バッハは、ジルバーマンが制作したピアノ
の試作品のいくつかを
弾いたことはあるものの、
あまり気に入らなかったらしい。
ピアノを最も早くから愛好した
作曲家としては、バッハの息子である
ヨハン・クリスティアン・バッハが
あげられる。父親が試作品を弾いてから
30年ほど後のことになる。
ロンドンに住んでいた彼がピアノを
好んで使ったことが、
若きモーツァルトなど、
あとに続く作曲家たちに広まる
一つの要因になった。
しかし、大バッハ
(ヨハン・ゼバスティアン・バッハ)が
ちょうど鍵盤楽器に大きな変革が起きる
時期に生きていたことは音楽の歴史に
とっては大きな意味があった。
ピアノの発明と同じぐらい重要である。
西洋音楽の歴史の中で最も重要だったと
言ってもいいかもしれない。
いわゆる「平均律」の普及に
大きくかかわっているからだ。
引用:「音楽の進化史」P.136
それまでは、単旋律の教会音楽が主流であり、
各楽器の調律は、音階ごとに
すべて調律しなおさなければならなかった。
それにより調性による
音楽の個性も研究されており、
教会旋法と言われる音階の域を
超えることがなかったのだが、
この時代に制作された「平均律」の楽器から、
音楽の歴史が変わっていったのである。
実際に採られたのは、従来使われていた
オクターブの構成音をいったん
すべて廃して、はじめから定義し直す
という方法だった。
今までの音はすべて捨て、改めて
1オクターブを単純に12分割したのだ。
隣り合う音と音の間の距離が
オクターブの中のどこをとっても同じ
になるようにした。
これは、1年を12か月、1か月を30日、
1日を24時間、1時間を60分に
分割するというのに似ている。
この調律、音階が現在「平均律」と
呼ばれているのものだ。
引用:「音楽の進化史」P.142
「純正律」から「平均律」に
変わることによって、
何か変わるかというと、
12音階すべてをあらゆる楽器が
その場で調律しなおさずに
演奏することができるということである。
これは、当時としては
画期的なイノベーションであり、
同じ音階の曲しかなかったものが、
同じ曲の中で転調し、そして
オーケストラで演奏するに
ふさわしい多重演奏の曲を
創ることができるようになったのである。
ここで、なぜこのバロック時代に
「平均律」が生まれたかという
興味深いエピソードがあったので
紹介してみたい。
「オクターブを均等に分割すればよい
のでは」という意見を唱える人はそれ以前
にも何人かいたが、どうすれば均等な分割
になるかをはじめて正確に計算したのは、
ヴィンチェンツォ・ガリレイだ。
彼は1581年に出版された著書
『古代の音楽と当代の
音楽についての対話』
の中で計算を試みている。
さらに、中国、明朝の皇子で学者であった
朱載堉も、1584年に出版された
『律呂精義』
の中で同様の計算をした。
ヨーロッパと中国の
地理的な距離を考えると、
ほぼ同時に同じことを
考える人が現れたのは
不思議だ。
なぜ、こういうことが起きたのか、
謎はまだ解けていない。
わかっているのは、
ともかく、両者の計算結果は同じだ
ということである。
ガリレイが計算に利用したのが
弦だったのに対し、主載堉が利用したのが
竹の筒だったという点が違うだけだ
(個々に長さが違う
36本の竹の筒を使った)。
彼らの計算によれば、
弦や筒の長さを隣り合う音の
94.38744パーセントにする、
ということを繰り返せば、
オクターブをちょうど
12分割できることになる。
1オクターブに12音ができたところで
弦や筒の長さがちょうど
元の半分になるわけだ。
引用:「音楽の進化史」P.142
ヴィンチェンツォ・ガリレイが1581年に、
はじめてオクターブを均等に割った計算を
正確に算出したが、
一方の東洋、中国でも朱載堉が
1584年の著書のなかで
同様の計算をし、同じ答えを導きだしたのだ。
これは、神が西洋と東洋の音楽に、
イノベーションを与えるべく
降ろされたと言っても過言ではないであろう。
バッハの凄さ②フーガの技法と天球の音楽
この「平均律」が生まれた時代、
ヨハン・ゼバスティアン・バッハは
古代ギリシャから受け継がれた
天球の音楽の思想、
音楽とは調和であり科学であり、
宇宙を貫く法則である
という思想を持ち、対位法の極致といわれる
フーガを作曲したのだ。
(追記※「平均律クラヴィーア曲集」の
解説によれば、序文に
「よく調律されたクラヴィーア」と
書かれており、正確には現代の
「等分十二平均律」ではなかったと思われる。)
そもそも音楽とは、まったく対照的な、
二つの矛盾した顔を持つ芸術である。
一方でそれは人の情念や本能に激しく
訴えかける神秘的な魔術である。
しかし他方で音楽は、
数学に極めて似ている。
抽象的な秩序であり、構造であり、
最も科学的な芸術なのだ。
実際、弦の長さの比率と音程の関係を
発見したピタゴラスをはじめ、
古代ギリシャにおいて音楽は
一種の科学だと思われていた。
また中国の古代思想のように、
音楽を宇宙の模像のように考える
伝統も珍しくない。
バッハの中には、
こうした数学的な音楽観が、
色濃く残っている。
彼の作品、とりわけフーガの類いは、
音で組み立てられた
一つの「小宇宙」であり、
「世界」の構造の鳴り響く
ミニチュアなのである。
引用:岡田暁生著「クラシック音楽とは何か」P.84
数は万物の根源であり、宇宙を貫く法則であり
神が創られた世界を表現するために
音楽は与えられたとするならば、
このバッハのフーガの意味が分かるであろう。
バッハの凄さ③音楽で神の創られた世界を表現した
神の創られた偉大なこの世界は、
完全に調和され、美しく、慈悲があふれ、
そして光に満ちている。
この世界の仕組みを、
音楽で表現するとどうなるか。
音楽は人々の魂に直接作用するが、
それは人の心が小宇宙であり、
大宇宙(マクロコスモス)と
小宇宙(ミクロコスモス)
が同じ法則で統べられているとするならば、
音楽によって神の世界を
垣間見ることができる
であろうと考えたのだ。
バッハの気が遠くなるような偉大さは、
まさにこの点にある。
音を秩序正しく配置して、
一つの小宇宙を組み立てていく
という点で、史上最高の作曲家が
バッハであったことは、
これまで何度も書いた。
少し卑俗な喩えかもしれないが、
まるでレゴブロックを
組み立てるようにして、
どんな音の「かたち」でも、
流れるように、自在にかけてしまう。
この点で彼を凌ぐ作曲家は
ただの一人もいなかったと断言できる。
ショパンやチャイコフスキーや
ワーグナーなど
バッハの足元にも及ばないし、
バッハには敵わなかった
と言っていいだろう。
そしてバッハの作曲技法の凄さが
最も端的にあらわれるのが、
対位法なのである。
引用:岡田暁生著「クラシック音楽とは何か」P.90
このことにおいて、バッハは音楽理論を
熟知していたのみならず、
神の創られた世界を、
キリスト教的神学観からみて、
宇宙の法則を実際に音楽で表わそうとした
最初の人物かもしれない。
霊的世界観を信じ、
神の恩寵を信じていなければ、
到底できるものではないのである。
バッハのフーガは、どれも神業のような
小宇宙だ。まるで物理学の法則のように、
法則から外れたことは何一つ生じず、
それ自体で完璧に調和している。
大小の無数の歯車が
精巧にかみ合わされて、
一分の狂いもなく時を刻み続ける時計に
似ていると言えるかもしれない。
引用:岡田暁生著「クラシック音楽とは何か」P.93
バッハはとても深遠であり、
奥深くありながら、
音楽技法に熟達して勤勉であったため、
1000曲を超える楽曲を生涯で作曲した。
宗教音楽は別途取り上げるが、
もう一つの側面としてのフーガについて、
その奥にある神学観をもとに紐解いた。
最後に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの
有名な「フーガの技法」を
聴いていただきたい。
更新の励みに、ランキングに参加していま9019"]す。
よろしければ、クリック応援お願い致します!