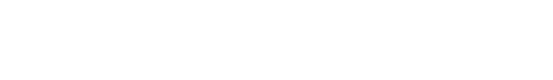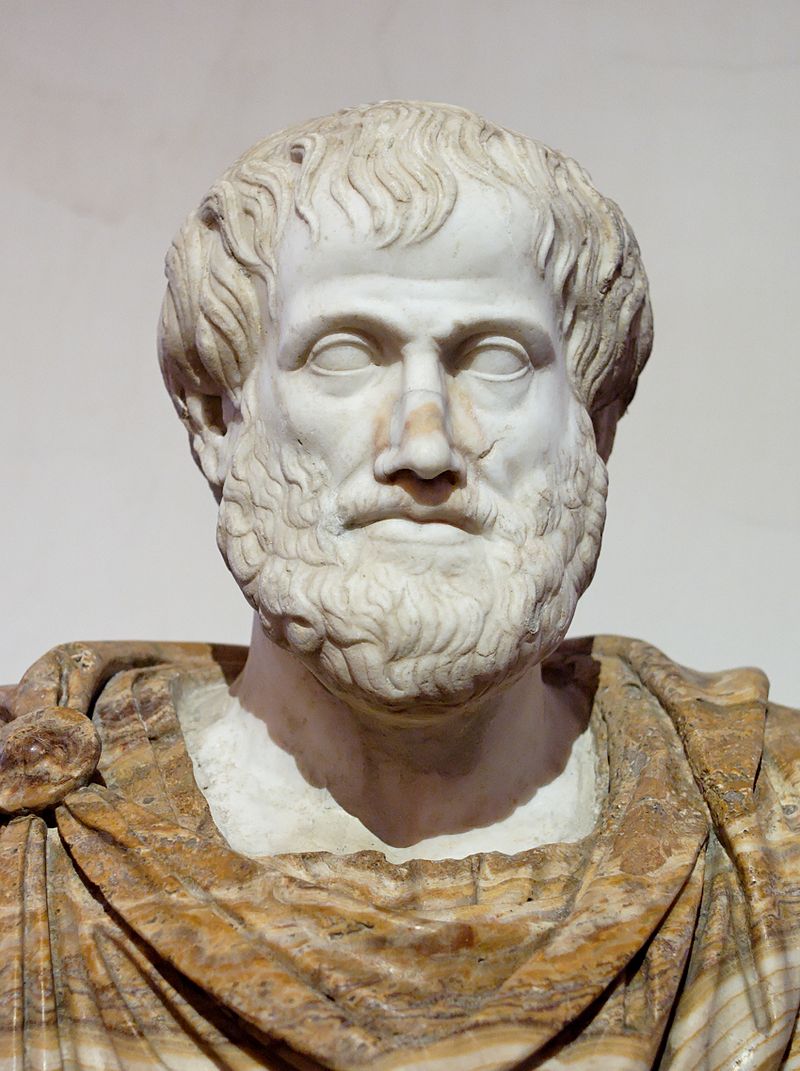今日は、アリストテレスと音楽について
探究してみたいと思う。
アリストテレスが説いた音楽が人格に及ぼす影響
アリストテレス(前384年 - 前322年)は、
古代ギリシャの哲学者として、
また「万学の祖」として有名であり、
西洋最大の哲学者の一人といわれる。
また、アレクサンダー大王の
家庭教師だったことも有名である。
プラトンの死後、
教え子アレクサンダーが大王に即位後、
アテナイにおいて
学園「リュケイオン」を開設した。
その学園の弟子たちと、
歩廊(ペリパトス)を散歩(逍遥)しながら
議論を交わしたことから、逍遥学派と呼ばれた。
そのアリストテレスが
音楽についてどのような意見を持っていたか、
少し紹介していきたい。
アリストテレスも、
音楽はよい人格を創るもの
であるから青少年に習わせる
べきだと主張した。
その根底には、音楽は魂の状態を
如実に反映するという考え方があり、
堕落した音楽を長く聴いていれば、
堕落した精神の人格となる、
という警告も含まれている。
引用:『ハーバード大学は「音楽」で人を育てる』
プラトンは、音楽は魂の調和を促すものとして
教育に取り入れようとしたが、
弟子のアリストテレスもまた、
音楽は良い人格を創るものであるから
青少年に習わせるべきと主張している。
ここで、アリストテレスの主張のなかで
大事な論点として考えるべきは、
音楽は魂の状態を如実に反映する
という考え方があり、
堕落した音楽を長く聴いていれば、
堕落した精神の人格となる、
という警告が含まれている、という点である。
これについては、
現代音楽に慣れ親しむ私たちでも、
少し思い当たる節があるのではないだろうか。
恥ずかしながら私は若い頃、ハードロックや
ヘビーメタルにハマっていた時期があった。
その頃の自分を回顧してみると、
日頃聴いている音楽の影響が、
青年期の人格にまで
影響を与えていたということを、
実感として感じるのである。
現代においては、アリストテレスのように
音楽が精神や人格に影響を及ぼすと
はっきりと主張する人はいないが、
私が若い頃聴いていた音楽が
ダークな音楽だっただけに、
性格や服装や考え方に影響を及ぼし、
仏教や哲学などを勉強して
音楽の趣味が変わっていくにつれ、
人格も変わってきたという実体験があるのだ。
衝撃的だが、
”堕落した音楽を長く聴いていれば、
堕落した精神の人格となる”、
という主張は真実であると感じる。

アリストテレスが説く音楽の旋法による性質の違いー『政治学』より
アリストテレスはたくさんの著作を残したが、
その中の『政治学』において、
音楽に関する記述がみられる。
音楽がどんな種類の
性質を持っているのか。
1音楽を聞くことが単に楽しい事であり、休息であり、心の悩みを取ってくれる、
そういった、遊び、休息の性質
2音楽は、体育のように体をある一定の性質のものにするように、音楽もまた、
習慣づけることによって、彼の性格を
一定の性質のものにする能力がある
だろうという、教育の性質
3良い時を過ごすという性質引用:アリストテレス『政治学』
音楽には、上記の3つの性質がある
と述べている。
要点を言い換えるならば、
【音楽の3つの側面】
遊戯や休息として役立つ
徳を形成するための重要な教育手段となる
高尚な楽しみや知的教養として貢献する
ということである。
そして音楽の調性について、
いくつかの言及がある。
『だれもが音楽が描写するものを
聞くならば、共感が生じてくるだろう。
それはリズムや旋律だけ
(この頃の音楽といえば、普通歌が
ついていた。これに関しては
いつか後述する予定)の場合にも起こる。
そして音楽の旋律そのものには
性格の相似がある。
例えば、混合リュディア調と呼ばれるもの
に対する反応は、哀しげで、重々しい、
他の種類のものでは
いっそう心優しいものに、
ドリス調は中庸で落ち着く、などと書き、
リズムに関しても同様で、
安定したリズム、
動きがあるもの、
少し卑俗的な物などもあるだろう。』
引用:アリストテレス『政治学』
音階法の本性にはそれぞれ相違がある。
混合リディア様式:
比較的に物悲しく
心の引き締まる気持ちにされる。
ドリス様式:
非常に落ち着いた気持ちにされる。
最も落ち着きのあるもので、
かつ最も男性的な性格を持つものである。
プリュギア様式:
熱狂的にする。ちょうど笛が楽器のうちで
もつような意義をもっている音階法。
すなわち、すべてのバッコス的熱狂や
それに類似の感動は
楽器の内では笛によって
最もよく表現され、音階法のうちでは
プリュギア様式の節において
それらに適した
表現を見出すのである。
リュディア様式:
行儀作法と同時に
教育を与える力を持ち得る
ことのために子供の年齢にも
ふさわしい性質を
一番多く持っているようである。
引用:アリストテレス『政治学』
このように、音楽の旋法によって、
ドリス様式のように男性的で、
最も落ち着きがあるとされる旋法もあれば、
プリュギア様式のように熱狂的で
笛が楽器のうちでもつような意義をもっている
音階、旋法もあるということなのだ。
ここでいうプリュギア=フリギアのことである。
良い性質を持つための音階としては、
アリストテレスは「ドリス様式」を称賛し、
「プリュギア様式」を感情的として
ふさわしくないとした。
アリストテレスの時代の音楽療法
また、古代ギリシャでは、
音楽療法としても旋法が
使われていた記述がある。
古代ギリシャ時代には、音楽は人の精神を
癒す効用があるとも信じられていた。
フリギア調で奏でる笛の音は、音楽療法に
適しているとされた。
アリストテレスの弟子テオフラストスは
「笛で奏でるフリギア調が
腰痛を和らげてくれる」と言っている。
また十九世紀のベートーヴェンは
弦楽四重奏曲第十五番作品一三二の
第三楽章を、
「リディア旋法による、
病より癒えたる者の
神への聖なる感謝の歌」として、静けさに
満ちた長大な楽章を書いている。
これは死の二年前、
作曲家本人が重大な病から
快復したのちに書いた曲で、
その心身を癒す意味が込められていると
解釈されている。
これは作曲技法として
旋法を用いるというより、
旋法が人間心理や気分を表すという、
古代からの音楽療法的な考えが
反映されていると考えられる。
引用:『ハーバード大学は「音楽」で人を育てる』
アリストテレスの弟子テオフラストスは、
「笛で奏でるフリギア調が
腰痛を和らげてくれる」
と言っている。
フリギア調で笛を奏でることで、
何か作用があるのかもしれない。
このフリギア調というのは、マイナー調だが、
スパニッシュなど熱狂的な楽曲が
生まれたという話もあるようだ。
また、ベートーヴェンは、
リディア旋法を、
心身を癒すための楽曲に用いた。
結局、アリストテレスと
音楽の探究で伝えたかったことは、
音楽に込められた調性や
メロディなどの効用によって、
人間の人格を良くしたり、
悪影響を及ぼしたりする力がある
ということなのだ。
たまには、現代に生きる私たちも、
昔の音階旋法で曲を創ってみることで、
新たな発見があるかもしれない。
更新の励みに、ランキングに参加しています。
よろしければ、クリック応援お願い致します!