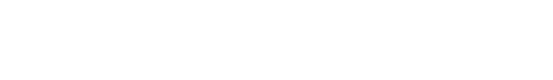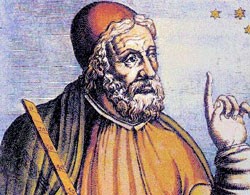今日は、プトレマイオスの
『ハルモニア論』について探究してみたい。
プトレマイオスとヨハネス・ケプラー
前回、アリストテレスと音楽
について探究したが、
その後の音楽論的系譜としては、
ピュタゴラス派で学びつつ、
アリストテレスの弟子となり、
『ハルモニア原論』を書いた
逍遥学派の哲学者、
アリストクセノス(紀元前375ー335)が
挙げられるだろう。
それから500年後、
エジプトのアレクサンドリアにて、
2世紀に生まれて天文学の権威となった
クラウディオス・プトレマイオス
(A.D.83-168)が
『ハルモニア論』を創り上げた。
このプトレマイオスは、
数学、天文学、占星学、音楽学、
光学、地理学、地図製作学など
幅広い範囲に業績を残した。
自らをピュタゴラス派とは呼ばず、
ときには批判的だったと言われているが、
”天球のハーモニー”という概念を研究し、
取り上げたことで
この概念に長い未来を与えたといわれる。
彼の業績は、
それ以前の考えや知識を受け継ぎ、
それに彼自身の天性の数学的才能を加えて、
以後千年以上にわたって
西洋の宇宙観を支配する
地球中心の天文学をまとめ上げたことである。
このプトレマイオスの『ハルモニア論』は、
執筆後1500年以上経って、
ヨハネス・ケプラーが読んだことで、
宇宙の音階を記述していた
第3巻の失われた章の
復元を試みるうちに
偉大な発見の糸口をつかみ、
思いがけなく科学史に
影響を与えることになったことは
非常に興味深く、
ロマンを感じるエピソードである。
(※プトレマイオスは地球中心説
(天動説)天文学の完成者であり、
ケプラーはプトレマイオスと
コペルニクス(地動説)の天文学を学び、
ケプラーの法則を発見し、最終的に
太陽中心説(地動説)の強化につながった。)
プトレマイオスの考案した宇宙の音階
プトレマイオスは、
ピュタゴラス派が唱えていた
天球のハーモニー、
数学的原理が天界の動きや
人間の魂の組成にいたるまで、
宇宙全体を支えているという考えに
賛同していたと言われている。
その研究のなかで、非常に興味深いのが、
ハルモニアの転位による「魂の転位」
という記述だ。
これらの思想を理論的に音階論に反映した
のが、天文学者プトレマイオスの
『ハルモニア論』であった。
オクターブ両端の楽音が基準音となる
トノス(オクターブ種、いわゆる旋法)が
変換すると、つまりハルモニアの
転位によってエートスの違いが生じ、
それが「魂の転位に一致する」
(『古代音楽論集』二七二頁)としている。
このように、古代から中世にかけては
音の響きと精神性が密接につながっている
と考えられていた。
引用:『ハーバード大学は「音楽」で人を育てる』
ハルモニア音階というのは、
いわゆる古代ギリシャ音階と考えるが、
そのハルモニア音階それぞれに
固有のエートスがあり、
ハルモニア音階の転位によって
エートスの違いが生じて、
それが「魂の転位に一致する」、
推測すると
魂に違う種類の影響を与える
という説である。
現代の平均律の全音階(長音階、短音階)
では転調してもあまり違いが分からないが、
古代ギリシャ音階それぞれの特徴が
魂に違った影響を与えると
考えられていたのだ。
そしてもう一つ、
プトレマイオスが考案した
天体のハーモニー、宇宙の音階
という大変興味深いものが
あったので紹介したい。
プトレマイオスが考案した天体の
ハーモニーの体系は、
それ以前のものより複雑だった。
初期のピュタゴラス派の人々は、
完全な音階ではなく八度と四度と
五度の音程を宇宙の配列に
結びつけたのかもしれない。
あるいは、10の天体から成る
宇宙は、中心火と外縁の火が
八度の音程にあり、
その間にある音程がすべて
埋まりさえすれば、
完全な音階を構成したかもしれない。
プラトンの「エルの物語」と
キケロの「スキピオの夢」には、
それぞれ八個と七個の音からなる
宇宙の音階が示されていた。
引用:『ピュタゴラスの音楽』
プラトンの「エルの物語」と
キケロの書いた「スキピオの夢」
にも宇宙の音階が示されていたようだが、
それを基にプトレマイオスが
考案した宇宙の音階というものがあった。
プトレマイオスの考案した宇宙の音階
地球 ハ(C)→月 二(D)→水星 変ホ(D#)→金星 ホ(E)→太陽 ト(G)→
火星 イ(A)→木星 変ロ(A#)→土星 ロ(B)→星々 二(D)
引用:『ピュタゴラスの音楽』
後世、さまざまな音楽理論家や神秘思想家が
宇宙の惑星と音階について述べていて、
それぞれが考える音と惑星の対比が違うのが
厄介なのだが、
この哲学としての天球の音楽の思想は、
17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーによって
天文学の発見につながっただけでなく、
幸福の科学における
「ベガの主神ヒームの霊言」に説かれる
宇宙全体を調和させている力が、
実はハーモニーである。
という内容とも一致するのだ。
以前にも紹介したが、
別の宇宙リーディングで
ハーモニーの宇宙について
語られている部分を紹介する。
・(質問者:三つの世界に共通する
ルール、法則はあるのか?)
・霊人①:その第三の世界は、
おそらくは、ハーモニーの世界なんで
はないかと思われるので、その世界は、
おそらく、巨大な宇宙交響楽が、あの、
奏でられているような世界
じゃないかと、いうふうに
思われるんですねえ。
宇宙自体が、
シンフォニーに包まれているような
世界なんでないかと、
いうふうに思われます。
宇宙全体が、有機的に、
楽譜みたいになっていて、
何かを表しているんですが、
それが、シンフォニーのように、
巨大な交響楽のようなものを、
宇宙自体が歴史で奏でている
みたいな世界が、
もう一つあるふうに見えるんです。
「宇宙人リーディングーアンドロメダ審議会は実在するか?」
ベガの主神ヒームの語られた内容や
この宇宙リーディングからみると、
ピュタゴラスという方も
その宇宙的真理を知っていたのではないか
と思わざるを得ない。
古代ギリシャ音楽と日本音楽の共通点
最後に、プトレマイオスの
『ハルモニア論』の解説本において、
面白い記述があったので紹介したい。
完全4度の音程をオクターヴに先立って
テトラコードという実践的な形態に
おいて原理的に認める点に、
古代ギリシア音楽の決定的とも言える
特質が認められる。
もちろんオクターヴ離れた二音の
同質性は同音という概念で経験的に
認められていたのだから、
この原理的な表象はオクターヴの
事実を排除するものではない。
オクターヴの調和の事実を
説明するにさいしても、
完全4度のエートスが原理として
採用されるのである。
この点において、古代ギリシア音楽は、
完全5度を原理とする近代音楽とは
対照的に性格づけられる。
古代ギリシア音楽には、
むしろ日本の伝統音楽に近いものがある
と予想されるのである。
引用:『古代音楽論集』
これによると、
古代ギリシャ音楽は、
完全四度の原理を基としており、
近代音楽は
完全5度の原理を基にしている
という違いがあるということなのだ。
これは大きな違いであるように
思えるが、
どれがどういう意味を持つかは
残念ながらまだ勉強不足で分からない。
以下のテトラコードの
説明をご覧いただきたい。
語源は古代ギリシアの4弦琴をさすが、
音楽理論用語としては完全4度の音程を
なす2音間に二つの中間音をもつ
4音音列を意味する。
ただし、この中間音の位置は固定された
ものではなく、その数もかならずしも
二つとは限らない。
古代ギリシアの場合、テトラコードは
音組織の基本的な単位とされ、
それを積み重ねることによって
完全音組織(シュステマ・テレイオン)
が形成された。
アラブ音楽では、弦楽器ウードの音律を
基本とした音組織が用いられたが、
これは完全4度枠に三つの中間音をもつ
テトラコードの積み重ねによって
体系化されていた。
日本音楽では、1オクターブ内の
二つの中心音(核音)が完全4度枠をなし、
そこに一つの中間音を含むテトラコードで
音組織が構成されているとみなされている。
なお、中世以降の西洋音楽では、
ヘクサコード(6音音階)が
音組織の基本的単位となり、
テトラコードはあまり
重要視されなくなった。
引用:日本大百科全書(ニッポニカ)
ここに書かれているように、
日本音楽も完全四度を原理とする
ということで、
古代ギリシャ音楽と日本音楽の
共通点もあったのだ。
更新の励みに、ランキングに参加しています。
よろしければ、クリック応援お願い致します!