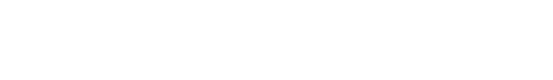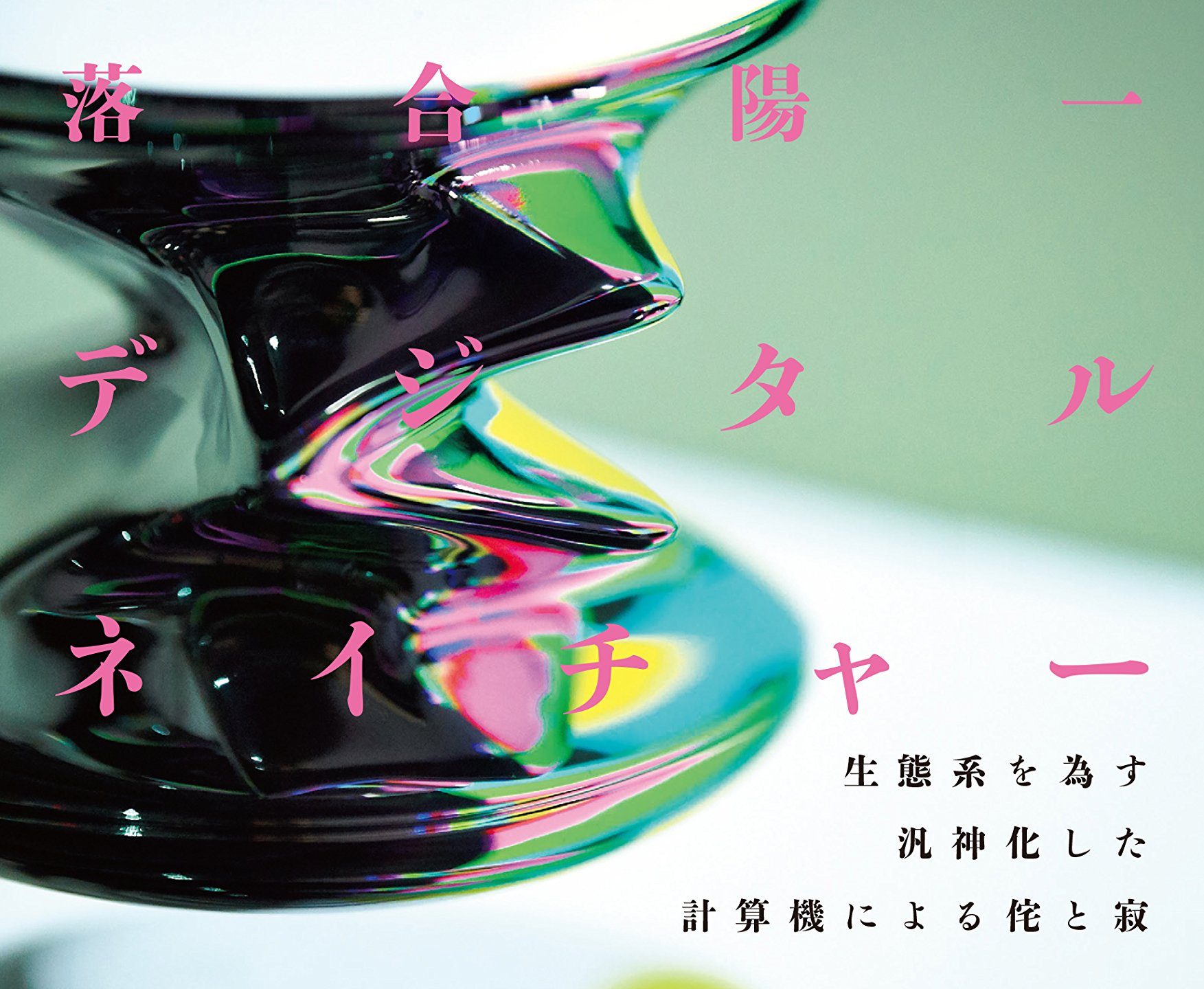今日は、落合陽一氏の『デジタルネイチャー』
第1章から、未来社会について考えてみたいと思う。
はじめに私のスタンスについて述べておくと、
落合陽一氏はある種の天才であり日本の
未来社会のビジョンを示しているという点で
凄い方だと思うが、あの世を信じ、
神を信じる信仰者の私としては、
人間機械論的な考え方については
ある種の危機感を抱かざるを得ない。
神や心の存在を信じる人と、
感情は頭脳の作用とする人との考え方の差には
大きな隔たりがあることは事実である。
しかしながら、新時代の潮流という方向について、
大きな時代の流れになるであろう
AI社会とデジタルネイチャーの未来を、
信仰者の立場から探究しようと試みるものである。
『デジタルネイチャー』という書籍については、
理系出身の私でもなかなか難解で
読み解くのが難しい印象だったが、
その中でも個人的に大いに感銘を受けた
箇所があったので紹介したい。
AI社会・デジタルネイチャーの未来
落合陽一氏は、『デジタルネイチャー』のなかで
次のように書いている。
我々の社会が抱えている最大の格差―
それは経済資本の格差ではなく
「モチベーション」と、そして
その根底をなす「アート的な衝動」を
持ちうるかの格差である。
現行人類のコンピューターに対して
優れている点は、リスクを取るほどに、
モチベーションが上がるところだ。
これは機械にはない人間だけの能力である。
逆にリスクに怯え、チャレンジできない
人間は機械と差別化できずに、
やがてベーシックインカムの世界、
ひいては、統計的再帰プロセスの世界に
飲み込まれるだろう。
引用:『デジタルネイチャー』P.66
AIが人間の仕事を代替していく社会では、
AI+VC型(ベンチャーキャピタル)と
AI+BI型(ベーシックインカム)に
二極化するといわれる。
機械を利用して新しいイノベーションを
興そうとするAI+VC型と、
機械の指示のもと働き、簡単かつ
少時間の労働を営みながら
ベーシックインカムを受給する
AI+BI型に分かれていく。
デジタルネイチャーとは、近代以前の多様性が、
近代以降の効率性や合理性を保ったまま、
コンピューターの支援によって実現される世界。
テクノロジーの進化によって、低コストで個人化
(パーソナライズ)が様々なものに適応される世界。
これは、言い換えれば近代のマスで提供された製品や
ソフトなどが、テクノロジーによって
意識することなく限りなくパーソナライズされて
多様な在り方として存在する世界ということであろう。
このデジタルネイチャー社会の最大の格差は
経済資本の格差ではなく、
「モチベーション」と「アート的な衝動」の格差だ
と説かれている。
「アート的な衝動」とは、個々人の文脈において、
それをせずにはいられない欲求・衝動を指すという。
AIのディープラーニング(機械学習)は
統計学的であるので、
最適化してリスクを避けようとする判断をし、
過去の事例にない新しいことを生み出したり、
チャレンジすることが苦手だ。
それに対し、人類がコンピューターに対して
優れている点は、
リスクを取るほどにモチベーションが上がるところ
だと書かれている。
逆にリスクに怯え、チャレンジできない人間は
機械と差別化できずに
AI+BI型(ベーシックインカム)として生きる
人間になってしまうということなのだ。
これはそもそも教育の問題かもしれないが、
企業家精神やクリエイティブなチャレンジができる
人間をどれだけ育てることができるか、
ということでもあると思う。
現行の教育システムのなかでは高学歴の秀才ほど
リスクを取りたがらず、
前例主義の安定志向である傾向があるため、
AI社会においては学歴のヒエラルキーが逆転する
可能性があるのだ。
逆に、学校教育において秀才と認められなくとも、
創造性やチャレンジ精神を身に付けた若者が、
クリエイティブクラスの仕事を
生み出して行く可能性を持っている。
これは、私をはじめ教育現場に携わる者にとっては
イノベーションを迫られる危機ではないだろうか。
デジタルネイチャー社会のモチベーションの一つは”信仰”
落合陽一氏は、加えて次のように書いている。
問題は、やりたいこととその衝動の
獲得方法があるかどうか。
リスクを顧みないほど何かに
熱中している人間や、
社会や技術の新しい芽を
育てたいという人間の数は、
実はごくわずかしかいない。
多くの人は知識を吸収しても、必ずしも
衝動を生み出すような独自の視座を
創り得ないからだ。
引用:『デジタルネイチャー』P.67
ここでは、リスクを顧みないほど熱中している
人間はごく少数で、
多くの人は知識を吸収しても、衝動を生み出す
独自の視座を創り得ないと説かれている。
そういったアート的で衝動となるほど
強いモチベーションを生むコンテクスト
は文化から生まれる。
そして、文化資本の再分配には、
資本以上に巨大な格差が存在する。
<中略>
今後は、文化の格差から生まれる
アート的なモチベーションの格差を、
いかに埋めていくかが
キーワードになるはずだ。
今後、機械と人間の融合が進むと、
機械学習では最適化できない
イノベーションの種は、そのような
衝動を持つ人間側に
求められるようになる。
引用:『デジタルネイチャー』P.67-68
アート的で衝動となるほど強いモチベーションは、
文化から生まれる。
そして、機械学習では最適化できない
イノベーションの種は、
そのような強い衝動を持つ人間側に
求められるということなのだ。
ここにおいて私は、AI社会におけるリーダーシップを
持つ可能性があるものの一つには、
”信仰”があると感じる。
なぜなら、利益至上主義でなくなったAI社会において、
アート的で強い衝動を持ち得る人間とは、
”信仰”を持つ人間も当てはまるのではないだろうか。
人間機械論的世界観と、信仰における霊的世界観と
は大きな価値観の相違があるが、
そこをうまく整合性をとって
社会システムを構築できるなら、
信仰を持つ人間ほど抽象的思考を持ち、これまで
地球上に前例のない理想社会(天上界のイデア)
をこの地上に降ろし、ユートピア社会を作ろうとする
理想家肌の人間も他にいないだろう。
これからの人類がやるべきことは、
「可能かもしれない想像上の産物」
に対して、「さまざまな質問を
問いかける」ために具体化して
「それに集中する」こと。
まだ実現していない未来にコミット
することは大きなリスクだが、
これが最も重要な価値である。
引用:『デジタルネイチャー』P.69
これからの人類がやるべきことは、
リスクを取って「可能かもしれない想像上の産物」
を具体化していくこと。
すなわち、デジタルネイチャーの社会にあって、
人間機械論に陥らず、
人間の尊厳や霊的世界の真実を知り、
霊的世界観に基づいて人間の幸福に寄与する
未来社会を構築すること。
そしてこれができるのは
神を信じる人間であろうと思う。
ぜひテクノロジーを嫌わず、
科学の利便性を活用しながら、
神の作られた世界を探究し続ける人材が
数多く出てくることを期待したい。
更新の励みに、ランキングに参加しています。
よろしければ、クリック応援お願い致します!